**コリジョン(collision)**は、主にネットワーク通信の分野で使用される用語で、信号の衝突や干渉を指します。
この現象は、複数の機器が同時に同じ伝送路を使用し、信号が衝突することで通信に支障をきたす原因となります。
この記事では、コリジョンの定義からその発生メカニズム、回避方法に至るまで、ITの専門的な視点で詳しく解説します。
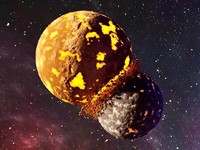
コリジョンの定義とその発生メカニズム
**コリジョン(collision)**とは、主に通信ネットワークにおいて、複数の機器が同じ通信経路を共有している場合に発生する信号の衝突現象を指します。
この現象は、信号波が干渉し、互いに崩れ合うことによって引き起こされます。
特に有線通信や無線通信で見られる現象で、通信の品質を低下させ、最終的にはデータの損失や遅延を引き起こします。
1. 有線通信におけるコリジョン
有線通信では、二台の機器間でのデータ通信において、通常は2本の信号線が使用されます。
これを全二重通信と呼び、信号が一方向にしか流れないため、コリジョンのリスクは減少します。
しかし、三台以上の機器が同じ伝送路を共有している場合、信号が同時に発信されることで、干渉が発生し、通信にエラーが生じることがあります。
例えば、イーサネット(Ethernet)ネットワークでは、複数のコンピュータが同一のケーブルを共有して通信を行っている場合、複数のデバイスがほぼ同時に信号を送信しようとすると、コリジョンが発生します。
この場合、送信されたデータが壊れ、再送信が必要となるため、通信効率が低下します。
2. 無線通信におけるコリジョン
無線通信においても、コリジョンは重要な課題です。
無線LAN(Wi-Fi)やモバイルネットワークでは、同じ周波数帯域を複数のデバイスが共有して通信します。
特に、無線通信では「帯域幅」を分割して複数のデバイスに割り当てたり、時間を分割して通信を行う方法が一般的です。
例えば、無線LAN(Wi-Fi)では、**CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**という技術が使われています。
これは、複数のデバイスが同じ周波数帯域を共有して通信する際に、通信が衝突しないように調整する仕組みです。
CSMA/CAは、通信を開始する前に他のデバイスが通信していないかを確認し、通信が空いているタイミングを見計らって信号を送信します。
3. コリジョン回避の技術
コリジョンを回避するためには、ネットワークの設計や使用する通信技術に工夫が必要です。
以下のような方法で、コリジョンを減らすことができます。
a. 有線ネットワークにおける回避方法
- 全二重通信(Full-Duplex): 二本の信号線を用いて、送受信を同時に行うことでコリジョンを回避します。
- スイッチングハブ(Switching Hub): 複数のデバイスが同じ伝送路を共有しないように、各デバイスをスイッチングハブに接続することで、コリジョンを回避します。
b. 無線ネットワークにおける回避方法
- FDM(周波数分割多重化): 複数の通信機器が同時に通信する場合、周波数帯域を分割して各デバイスに割り当てる方法です。
- TDM(時間分割多重化): 同じ周波数帯域を複数のデバイスが使用する際、通信を時間的に分けて行う方法です。
コリジョンの影響と解決策
コリジョンが発生すると、通信速度が遅くなる、パケットロスが増える、通信が不安定になるといった問題が起こります。
特に、**リアルタイムアプリケーション(VoIPやオンラインゲーム)**では、コリジョンによる遅延や音声・映像の乱れが顕著に現れることがあります。
したがって、ネットワークの設計においては、コリジョンが発生しないように十分な配慮をする必要があります。
これには、適切な通信プロトコルの選定、ネットワークトポロジーの構築、通信帯域の最適化などが含まれます。
まとめ
コリジョンは、通信ネットワークにおいて避けられない現象ですが、適切な設計と技術を導入することで、その影響を最小限に抑えることができます。
特に、有線通信と無線通信でのコリジョン回避技術には、それぞれ特徴的なアプローチがあります。
これらの技術を理解し、適切に運用することで、ネットワークの通信品質を向上させ、効率的なデータ通信を実現することが可能です。
