近年、企業のITインフラが高度化する中で、自社設備だけで安定的・効率的な運用を行うのは難しくなっています。
そうした課題を解決する方法として注目されているのが、ハウジングサービス(housing service) です。
本記事では、ハウジングサービス の仕組み、コロケーションサービスとの違い、そして導入によるメリットや実際の活用シーンまで、IT視点から詳しく解説していきます。
ハウジングサービスとは?
基本定義
ハウジングサービス とは、サーバや通信機器などのIT機器を、専用の施設(多くはデータセンター)内に設置して運用できるよう、スペースとインフラ環境を貸し出すサービスです。
この施設には以下のようなハード・ソフト両面のインフラが整備されています:
-
高速かつ冗長性のあるインターネット回線
-
大容量の配電設備と無停電電源(UPS)
-
空調や冷却機構
-
耐震・免震構造
-
24時間365日の入退室管理システム
顧客による持ち込み機器の設置
利用者(企業や法人など)は、自社で所有する機器を持ち込み、施設内のラックまたは専用区画に設置します。
そして、リモート操作によって外部から機器の管理や運用を行います。
物理的なトラブル発生時には、現地に赴いてメンテナンスを行うことも可能です。
コロケーションサービスとの違い
ラック単位 vs. 区画単位
ハウジングサービス と コロケーションサービス(colocation service) は、しばしば同義で使われますが、厳密には対象となるスペースの単位が異なる場合があります。
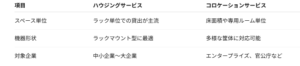
どちらも「自社保有の機器を安全に運用するための場所とインフラ」を提供するという点では同じですが、規模や要件に応じて使い分けられます。
ハウジングサービスの主な機能と付加サービス
標準提供される機能
-
電源・回線の冗長構成
-
ネットワーク接続(BGPやマルチキャリア対応)
-
24時間遠隔監視システム
-
出入口管理およびセキュリティカメラ
付加サービスの例
-
稼働監視や死活監視(Ping/HTTPなど)
-
障害検知と自動通知(SNMP対応)
-
データバックアップやリストア作業
-
ネットワーク機器やサーバのレンタル・設置代行
これらにより、オンサイトのIT人員を減らしつつ、プロレベルのインフラ管理が実現 できます。
なぜハウジングサービスを導入すべきか?
コストと柔軟性の最適化
自社でデータセンター設備を保有・運用するには、膨大な初期投資と人件費が必要です。
ハウジングサービスを利用することで、初期費用を抑えながら、柔軟で信頼性の高い運用基盤を実現 できます。
災害リスクへの備え
多くのデータセンターは、地震や停電などの自然災害への対応が施されており、BCP(事業継続計画)対策としても有効です。
都市圏から離れた立地に分散設置することで、データ消失やサービス停止のリスクを最小化します。
ハウジングサービスの導入例
例1:ECサイト事業者
アクセス数が多い大規模ECサイトは、トラフィックやデータベース負荷に耐えるため、ハウジングサービスで高性能な自社サーバを安定運用しています。
例2:金融・証券業界
セキュリティと冗長性が最重要な金融業界では、ハウジング施設を利用して、基幹システムを信頼性の高い環境で運用するのが一般的です。
まとめ
ハウジングサービス は、企業がITシステムを安定かつセキュアに運用するための強力な選択肢です。
設備投資を抑えつつも、高可用性・高セキュリティ・高拡張性 を兼ね備えた環境を手に入れることができます。
また、コロケーションサービス との違いを理解し、企業の規模やニーズに応じた選択を行うことで、より最適なITインフラ戦略を構築できます。
今後、クラウドとオンプレミスのハイブリッド化が進む中で、ハウジングサービスはその中核を担うインフラとして、ますます重要性を増していくでしょう。
