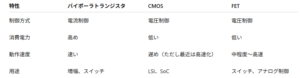バイポーラトランジスタ(Bipolar Junction Transistor, BJT)は、古くから利用されている基本的な半導体素子の一つであり、今日でも多くの電子機器やIT機器に欠かせない構成要素です。
信号の増幅やスイッチングといった重要な機能を持ち、アナログ回路・デジタル回路の両方に応用されています。
本記事では、バイポーラトランジスタの構造や動作原理、NPN型とPNP型の違い、そしてFETとの比較や具体的な使用例まで、ITエンジニアや電子設計者に役立つ形で詳しく解説します。
バイポーラトランジスタの基本構造と特徴
バイポーラトランジスタとは?
バイポーラトランジスタは、N型半導体とP型半導体を交互に接合して構成されるトランジスタで、電子と正孔(ホール)という2種類のキャリアを用いるため「バイポーラ(二極性)」と呼ばれます。
ユニポーラトランジスタとの違い
これに対し、FET(電界効果トランジスタ)などは、主に片方のキャリア(電子または正孔)だけを利用するため、「ユニポーラトランジスタ」と呼ばれます。
バイポーラトランジスタは電流制御型、FETは電圧制御型という大きな違いがあります。
3つの基本端子
バイポーラトランジスタは以下の3端子構成を持ちます:
-
エミッター(Emitter, E):キャリアを放出する
-
ベース(Base, B):制御信号を受ける
-
コレクター(Collector, C):電流を受け取る
この構造により、ベース-エミッター間に少量の電流を流すことで、コレクター-エミッター間に大きな電流を流すことができる(電流増幅)という特性を持ちます。
NPN型とPNP型の違い
NPN型トランジスタ
-
構成:N型 – P型 – N型
-
特徴:電子が主なキャリア
-
動作:ベースに小さな正の電流を流すことで、コレクターからエミッターに大きな電流が流れる
![]()
NPN型は、正電源での動作がしやすいため、一般的に多く使用されています。
PNP型トランジスタ
-
構成:P型 – N型 – P型
-
特徴:正孔が主なキャリア
-
動作:ベースに小さな負の電流を流すことで、エミッターからコレクターへ電流が流れる