公開鍵暗号(public key cryptosystem)は、現代のITセキュリティに欠かせない非対称鍵暗号方式の代表格です。
データの暗号化と復号を異なる鍵で行うこの方式は、情報通信・インターネット取引・本人認証など、広範な分野で活用されています。
本記事では、公開鍵暗号の仕組み・数学的背景・セキュリティ技術との関係性について、専門的な観点から詳しく解説します。
公開鍵暗号の基礎知識
公開鍵暗号とは?
公開鍵暗号は、暗号化に使用する鍵(公開鍵)と、復号に使用する鍵(秘密鍵)を別に持つ非対称暗号方式です。
この構造により、鍵を安全にやり取りする問題が大幅に軽減され、セキュリティが向上します。
-
公開鍵は誰でも入手可能
-
秘密鍵は本人だけが保持
-
公開鍵から秘密鍵を推測するのは計算上非常に困難
この原理は、1976年にDiffie-Hellman鍵交換として提唱され、1977年にRSA暗号として初めて実用化されました。
公開鍵暗号の仕組みと特徴
暗号と復号のプロセス
-
受信者は自分の公開鍵を送信者に渡す
-
送信者はそれを使ってメッセージを暗号化
-
受信者だけが、自分の秘密鍵でメッセージを復号化
このように、機密性の高い通信が可能になります。
例:送金アプリでの使用
銀行の送金アプリでは、ユーザーの公開鍵を用いて送金データを暗号化し、サーバー側でのみ復号できる仕組みになっています。
これにより、第三者による盗聴リスクを防げます。
秘密鍵解読の困難性
RSA暗号では、巨大な素数の積を用いて鍵が生成されます。
これは「素因数分解の困難性」という数学的前提に依存しており、現代の計算機では現実的に解読不可能とされています。
その他の数学的根拠:
-
ElGamal暗号・Diffie-Hellman鍵交換:離散対数問題
-
楕円曲線暗号(ECC):楕円曲線上の離散対数問題
公開鍵暗号の利点と課題
メリット
-
鍵の配布が安全:通信相手に公開鍵を渡すだけで済む
-
中間者攻撃のリスクが低下
-
ハイブリッド暗号方式との併用で高効率
デメリット
-
処理が複雑で重い
-
暗号強度を確保するには高い計算コストが必要
-
モバイルやIoTデバイスでは性能が課題となることも
公開鍵暗号の応用分野
デジタル署名と真正性の検証
デジタル署名(Digital Signature)とは、メッセージの真正性を保証する技術で、秘密鍵で署名し、公開鍵で検証する仕組みです。
使用例:
-
ソフトウェアの配布元確認
-
契約書の電子署名
-
電子政府のオンライン手続き
受信者は公開鍵で検証を行い、改ざんの有無や送信者の信頼性を判断できます。
PKI(公開鍵基盤)と証明書
PKI(Public Key Infrastructure)は、公開鍵の信頼性を確保するための枠組みで、以下の要素で構成されます:
-
公開鍵証明書(Digital Certificate)
-
認証局(CA):証明書の発行・署名を行う
-
ルート証明書:Webブラウザなどに事前搭載されている
PKIにより、信頼性のある公開鍵交換がインターネット上で可能になります。
公開鍵暗号と共有鍵暗号の違い
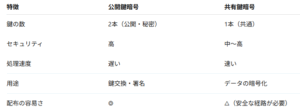
ハイブリッド方式の活用
実際のシステムでは、両者を組み合わせたハイブリッド暗号方式が主流です。
-
公開鍵暗号:鍵の配送
-
共有鍵暗号:通信データの暗号化
例:TLS(HTTPS通信)では、公開鍵暗号でセッション鍵を交換し、その後の通信は共有鍵で行われます。
まとめ
公開鍵暗号(public key cryptosystem)は、ITセキュリティの中核技術であり、次のような特徴を持っています:
-
非対称な暗号化で安全な通信を実現
-
デジタル署名やPKIによる真正性保証が可能
-
共有鍵暗号とのハイブリッド運用で高効率を実現
近年では、量子耐性暗号への移行や、ブロックチェーン技術との連携も注目されています。
エンジニアやセキュリティ担当者にとって、公開鍵暗号は必須知識であり、今後も進化を続ける重要な分野です。
