NAS(Network-Attached Storage)は、現代のデータ管理やバックアップに欠かせない存在です。
本記事では、NASの基本的な仕組みから、企業・家庭での活用例、DASとの違い、導入時の注意点まで詳しく解説します。
ネットワーク経由で使えるストレージを探している方や、NASの導入を検討しているIT担当者の方に向けて、実用的な知識を提供します。
NASとは?ネットワーク越しに使えるストレージの基本
NASの定義と仕組み
NAS(Network-Attached Storage)とは、LAN(ローカルエリアネットワーク)に直接接続できる外部記憶装置です。
簡単に言えば、ネットワーク経由で複数のコンピュータからアクセスできるファイルサーバのような役割を果たします。
構成要素としては以下の通りです:
-
ハードディスクやSSDなどの記憶装置
-
ネットワークインターフェース
-
軽量なOS(Linuxベースが主流)
-
Webブラウザから操作可能な管理ソフトウェア
これらが一体となった専用ハードウェアによって、低コストでの導入と運用が可能となっています。
NASの主な用途と実用例
家庭での利用例
-
写真・動画・音楽の一元管理
スマートフォンやデジカメで撮影したデータをNASに保存し、家族全員がアクセス可能に。 -
テレビ録画の保存先としての活用
Blu-rayレコーダーやHDDレコーダーと連携し、録画データの保存・再生に利用されるケースが増えています。
企業での利用例
-
部署間でのファイル共有
NASを社内ファイルサーバとして利用すれば、部門間のデータ共有がスムーズに。 -
バックアップとアーカイブの自動化
スケジュール機能を使って、定期的なデータバックアップを自動で行うことができます。
DASとの違いとは?
DAS(Direct-Attached Storage)とは
DASは、PCやサーバに直接接続されたストレージ装置(USB接続のHDDや内蔵SSDなど)です。
ネットワークを介さず、1台のコンピュータでのみ利用可能なのが特徴です。
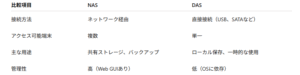
このように、共有性と拡張性を重視する場合はNAS、速度と単独使用を重視するならDASが適しています。
高機能なNASの特徴と選び方のポイント
RAID機能と冗長性
ビジネス用途では、RAID(Redundant Array of Independent Disks)機能を備えたNASが推奨されます。
これにより、ディスク障害時のデータ保全性が確保されます。
-
RAID1:ミラーリング(同じデータを2台のHDDに保存)
-
RAID5:複数ディスクによる分散パリティ保存
-
ホットスワップ対応:稼働中のディスク交換が可能
対応プロトコルとOS互換性
NAS製品の多くは以下の通信プロトコルに対応しており、Windows・macOS・Linuxいずれの環境でも利用可能です。
-
SMB/CIFS(Windowsネットワーク共有)
-
NFS(Linux/Unix向け)
-
AFP(Apple Filing Protocol:macOS)
導入前に知っておくべき注意点
セキュリティ設定
インターネットに接続されたNASは、外部からの不正アクセスのリスクがあります。
初期設定後は、以下の対策が必須です。
-
管理パスワードの強化
-
ファームウェアの定期的な更新
-
ファイアウォール・ポート制限設定
容量と将来の拡張性
-
予想されるデータ容量の2倍以上を目安にしておくと、将来的なストレージ不足を防げます。
-
HDDの交換や増設が容易なモデルを選ぶと運用がスムーズです。
まとめ
NAS(Network-Attached Storage)は、企業や家庭におけるデータ共有・保存・バックアップの効率化を支える重要なITインフラです。
特に以下の点がポイントです:
-
ネットワーク経由で複数デバイスから同時アクセス可能
-
ファイルサーバ代替としての活用が可能
-
RAID対応NASならデータ保護性能も向上
-
DASとは用途・構造が異なるため、目的に応じた選定が重要
適切なNASを選ぶことで、セキュアかつ効率的なデータ管理環境を構築することができます。
これからNASの導入を検討している方は、この記事の内容を参考にして、自社や家庭に合ったストレージ環境を整えてください。
さらに参考してください:
NAP(ネットワークアクセス保護)とは?Windowsセキュリティ機能でネットワークを守る
