ネットワークトポロジー(network topology) は、ITインフラの設計において欠かせない基礎知識の一つです。これは、ネットワーク内のノード(PC、サーバー、ルーターなどの機器)がどのように接続され、データがどのように流れるかを示す構造です。
この記事では、ネットワークトポロジーの基本から応用、物理・論理の違い、そして各構成のメリット・デメリットまでを、実例を交えながらわかりやすく解説します。
ネットワークトポロジーの基本
ネットワークトポロジーとは?
ネットワークトポロジー とは、ネットワークを構成するノード間の接続パターンや構造を指し、主に 物理トポロジー と 論理トポロジー に分類されます。
通信の効率性や安定性に大きく影響するため、適切な設計が求められます。
-
物理トポロジー(Physical Topology):実際の配線や物理的な接続構造
-
論理トポロジー(Logical Topology):信号の流れや論理的な通信パターン
たとえば、物理的にはスター型でも、信号がバスのように一方向に流れる場合は、論理的にはバス型となります。
主要なネットワークトポロジーの種類と特徴
スター型(Star Topology)
スター型は、各ノードが中央のハブやスイッチに接続される構成です。
-
メリット:障害の影響範囲が限定的/保守が簡単
-
デメリット:中央機器の故障で全体に影響
企業ネットワークやオフィスLANで多く採用されている構成です。
バス型(Bus Topology)
バス型は、1本の共有通信路(バス)に複数のノードを接続する方式です。
-
メリット:配線が簡単でコストが低い
-
デメリット:データ衝突のリスクが高く、信頼性が低い
現在はあまり使われていませんが、初期のEthernetで採用されていました。
リング型(Ring Topology)
リング型では、ノードが環状に接続され、データが一方向または双方向に流れます。
-
メリット:信号の順序制御がしやすい
-
デメリット:1箇所の障害が全体に影響する可能性あり
FDDI(光ファイバを使用したネットワーク)などで利用されていました。
メッシュ型(Mesh Topology)
メッシュ型は、各ノードが複数の他ノードと接続される構成です。
-
メリット:高い冗長性/通信経路の自由度が高い
-
デメリット:配線コストが高い/構成が複雑
大規模ネットワークやバックボーンネットワークで使われます。
ツリー型(Tree Topology)
ツリー型は、スター型を階層的に拡張した構成で、上位から下位ノードに枝分かれします。
-
メリット:拡張性が高く管理がしやすい
-
デメリット:上位機器に障害があると下位に影響
企業の大規模LAN構成などで一般的です。
デイジーチェーン型(Daisy Chain)
ノードが直列につながる構成で、主に小規模なデバイス接続(例:IoT機器)などに利用されます。
物理トポロジーと論理トポロジーの違い
物理トポロジーと論理トポロジーは、しばしば混同されますが、設計上明確に区別する必要があります。
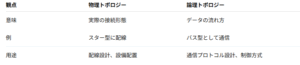
たとえば、リピーターハブで接続されたEthernet LANは、物理的にはスター型でも、内部的にはバス型の論理トポロジーとなります。
通信規格とトポロジーの関係
通信規格(例:Ethernet、Token Ring)は特定のトポロジーに基づいて設計されていることが多く、これを無視した接続構成ではネットワーク障害の原因になります。
例:
-
Token Ring:物理的にはスター型だが、論理的にはリング型
-
Ethernet(古典的なもの):バス型論理トポロジーを前提
誤ったトポロジー構成により、信号のループやパケットの衝突が発生し、ネットワーク全体が停止するリスクもあります。
まとめ
ネットワークトポロジーは、ITインフラ設計の基盤であり、効率的かつ安定した通信のためにはトポロジーの理解が不可欠です。
-
トポロジーにはスター型、バス型、リング型、メッシュ型、ツリー型など複数の種類があり、それぞれに利点・欠点があります。
-
物理トポロジーと論理トポロジーを正しく理解し、使用する通信規格に応じた構成を選ぶことが重要です。
-
正しいトポロジー設計は、ネットワークの信頼性と保守性を大きく向上させます。
ネットワーク設計を行う技術者や学習者にとって、トポロジーの理解は必須スキルです。
